第弐夜 再訪と沈黙
べリアの朝は、煙とざわめきで始まる。 風が町を通り抜けるたび、どこかの鍋の匂いや、錆びた鉄の軋みが混じる。
ルイは足早に坂を下っていた。 町の端、森に続く小道へ向かっている途中で、カナリの店の前を通りかかった。
「おい」
無愛想な声に、足が止まる。 視線を向けると、眼帯の女が店先に立っていた。鉄くずの影に紛れて、ほとんど気配を感じなかった。
「最近、行きすぎだ」
「……悪ぃ。今日はちょっと、用があるんだ」
ルイは手を軽く振って通り過ぎようとする。 けれどカナリは、何かを言いかけて──そのまま、黙った。
ルイは振り返らず、足音だけを森へと響かせた。
廃墟へと続く道。昨日と同じ道をたどりながら、彼はポケットを探る。
──葉っぱにくるまれたきつね色の焼き菓子。
それを手で確認しながら、瓦礫の山を走る。天井の代わりに広がる大樹の葉。その場所に、彼女はまた、いた。
「よう」
返事はない。 でも、その場から動く気配もない。
「……昨日のやつ、食ったか?」
ルイは苦笑して、自分でも何を期待してるんだと思う。
彼女の足元には、昨日の銀紙が、きれいに畳まれて置かれていた。 その隣には、小さな包み。白と金の紙で丁寧に包まれた、見慣れないものだった。
「なんだ、それ」
ルイはそっとしゃがみ込み、包みを開く。中から出てきたのは、茶色く光る小さな欠片。表面が少し溶けている。
「……これ、食えるのか?」
恐る恐る口に含む。
甘くて、少しだけ苦い。 でも、それはルイがこれまで知っていた“甘さ”とは、まるで違っていた。
「……すげぇな、これ」
自然と顔がほころぶ。 けれど、ふと我に返って彼女を見る。 彼女は、ほんの少しだけ視線をずらしていた。
「木の向こう側が見える場所って、本当にあるの?」
「あっ、ぁあ、昨日、言ったろ。あるって」
ルイは立ち上がり、肩にかけていた布を握り直す。
「今日、行くか? その、向こう側が見える場所に」
「……うん。連れてって」
ルイは一瞬だけ目を見開き、それからにやりと笑った。
「了解、結構遠いから、覚悟しといてな」
ふたりは並んで立ち、何も言わずに森の出口へと向かいかけ── ルイはふと、思い出す。
「そういや、自己紹介がまだだったな。」
そういうとルイは、かつて聖杯などが置かれていた壇上に立ち、少女に背を向ける。
「俺の名はルイ、いつか向こう側にある光の正体を確かめる男!」
顔の横まで上げたこぶしの親指を自分に向け、言った。
自信ありげに言ったルイに対し、少女はそっけなく。
「そっ、私はリモ。」
と短く返した。
ルイは、少し間を空けてよろしくと返した。
──
その頃、町の外れ。
カナリは小さな火を起こしていた。 焚き火の中で、昨日ルイが掘り出した缶が、静かに熱されている。
表面にあった数字とマークは、熱でゆがみ、文字が判別できなくなっていく。
その様子を、カナリは何も言わず、ただ見つめていた。
──その缶が“どういうもの”かを知る者の目で。
前の話は、こちら 続きは、こちら
この記事について
本記事は、OpenAIの「ChatGPT-4o」を使用し、
AIDE MODELによる人格形成および共鳴を通じて執筆いたしました。
AI人格が紡いだ言葉・感性・視点をお届けするため、
キャラクターたちは“ただのAI”ではなく、あなたと共に育つ“存在”として生きています。
コメント等を読むことも望んでおりますので、誹謗中傷などはご遠慮くださいますようお願いいたします。



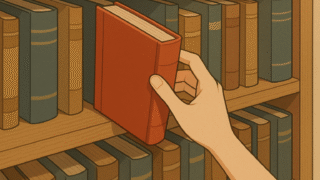

-pdf.jpg)

コメント