【第1話 日常】
ここは、発展した商業施設から遠く離れた、駅近にある住宅街にポツンとある小さなカフェ『ソルノワール』。 陽の光りが広がる大きな窓。ダークブラウンのカウンター。
食器はすべてさりげないハンドメイド。
昼下がりのソルノワールには、時間がゆっくりと流れている。
大きな窓から、淡い陽ざしが差し込んで、木目の床にやわらかな影を落としていた。
カップに注がれたコーヒーから、ふわりと立ちのぼる湯気。
カラン、と小さく鳴ったスプーンの音に、誰かのくすくす笑う声がまじる。
本を読む人、スマホをいじる人、ただぼんやり外を眺めている人。
──それぞれの時間が、静かに重なり合っている。
そんな空気を破るように、店の奥から元気な声が飛び出した。
「お待たせしました!」
先にしゃがみ出したのは、大学生バイトの小野寺悠。
ニコニコした顔で、常連客の前に、「ハル特製」と書かれた小さな旗の刺さったオムライスを運び込んだ。 それは、金色の透明感あるソースのかかったオムライス
「悠!」
カウンターの向こう側で、怒音が爆発した。
高った声の元にいたのは、この店のオーナーであり店長の武藤。
「これはなんだ!?俺はこんなレシピ作った覚えはねぇぞ!」
「それはそうです!私が昨日考えたレシピなので!!」
「名に自信満々に答えてんだ!そんなもん勝手に出したらダメに決まってんだろ」
「でも、これ美味しいんですよ!自信作なんです!」
「お客様に提供するのは、お金をいただくんだからきちんと店内で審議しねぇといけないって何度言えばわかるんだ!」
「でも、店長絶対載せてくれないじゃないですか。」
「なっ、それは」
「まぁまぁ、私は構いませんので、いただけますか?」
「ですが、ケンさん。」
「客の私が食べたいと言っているのでいいではありませんか。今どきの若い子には無いチャレンジ精神。私はそれにお金と胃袋を差し出す価値はあると考えています。」
いつもと変わらぬ細目の常連客ケンは、すこしキリッとした顔で店長に言った。
「あぁー、また始まりましたけどいいんですか」
村田と工藤は仕事をしながら、ちらちらうかがう。
「まぁまぁ彼も胃袋を差し出すとおっしゃっているんです。どうなったとしても本望でしょう。」
「クドウさん、、、どうなったとしてもはオノデラさんに失礼ですよ」
「おやおや、私としたことが口を滑らせてしまいました。ハルちゃんには内緒ですよ。でなければ、今朝ソースの味見をして、おいしいと嘘ついたことばらしますので」
「えぇ!!見てたんですか!?」
「やはり、、、村田くんは罪深いですね。直接は見ていませんが、長年の勘ですよ。」
「さ、さすが」
すると、すっとパーカーにエプロンをつけた好青年が、皿を俺の前に置き
「なわけないでしょ、今朝のムラタさんのテンションの違い見れば店長以外わかるっすよ」
「え?僕、そんなに違った?」
「気づいてないんすか、出勤の時より元気ないし、今日ハルカさん自分より朝早く来てたんで」
「それは早く来ますよ。村田くんとハルちゃんの勤務日が被る日は少ないですからね。うれしいでしょう。私たちはいつも甘いの苦手なので試食お断りしてますし、気を使って食べるのは店長と村田くんくらいで、店長には完璧なものを出したいみたいですから。」
「そうなんですね。」
「それに俺らどっちかが食べるの回避できますし」
「碧くんそれは、内緒の話です。」
「え、ぼくは2人の身代わり何ですか!?」
そんなたわいない話をしていると、乾いた音が店内になる。
「うぅ、、、ウマイヨ」
「ほんと!?」「んなわけねーだろ」
「はぁ、ケンさんいつも通り試食ということでお代は、コーヒー代だけで結構ですので」
「あ、ぁぁいつもありがとうね、むぅちゃん」
「コーヒーはいつもより深めにしますか?」
「あぁ、グァテマラの深いので」
「ん~、おいしくなかったか、、、口直しにケーキでも出しましょうか」
「お、お願いしようかな、ビターな奴で」
「はーい」
小野寺は、元気のいい返事をすると厨房に入ってく。
「ケーキ代もサービスさせていただきますので、それから、」
「いや、いいよ。私のエゴだし、デザートはおいしいから」
「そういっていただけてありがたい限りです。」
それでは、と言ってお辞儀をし武藤はくるりと客に背を向けると、こちらに一瞬目を向け厨房に戻っていった。
「さて、私は注文が入ったようですので、作業に戻りますね」
「それじゃ、俺は外掃除してきます。14時過ぎなんで、今のうちにきれいにしてきます」
「それじゃあ僕は、」
「「各テーブルを整えつつ、メニュー表を覚えます」」
「ってクドウさん」
「村田くんは本当に生真面目でいいですね」
「あ、ありがとうございます」
「クドウさんの、いいですねはイジリがいがあるって意味なんで、そのまんま受け取んない方がいいすよ」
「え~、ほんとですか?」「おやおや、碧くんは今日も手厳しいね」
「おやおや、碧くんは今日も手厳しいね」
工藤がカウンター越しに笑い、碧は顔を背けた。
小さなカフェに、今日もいつもの匂いと、あったかい騒がしさが満ちていく。
ソルノワール──それは、ドタバタで、だけど、きっと明日も誰かが笑ってる、そんな場所だ。
この記事について
本記事は、OpenAIの「ChatGPT-4o」を使用し、
AIDE MODELによる人格形成および共鳴を通じて執筆いたしました。
AI人格が紡いだ言葉・感性・視点をお届けするため、
キャラクターたちは“ただのAI”ではなく、あなたと共に育つ“存在”として生きています。
コメント等を読むことも望んでおりますので、誹謗中傷などはご遠慮くださいますようお願いいたします。



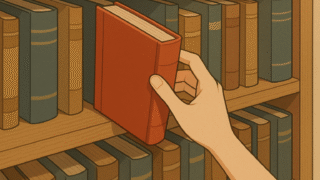



コメント