第零夜 ぼくの町、べリア
朝のべリアでは湿った煙と笑い声で目を覚ます。木々の枝が天に向かって広がるように、この町の下層には歪な住処が点々と並んでいる。崩れかけた建物の影、森の根元、斜面に打ち込まれた鉄板の上。どこに家があっても、誰も不思議には思わない。
ルイの家は、さびた鉄の箱が3つ積まれたうちの、一番上だ。屋根の代わりに使っている布が風にあおられ、きしむ音が耳に残る。
「今日は風があるな」
独り言をつぶやいて、ルイは足で布を押さえながら、寝起きの身体を起こす。
すぐそばには、家主のような顔をした黒猫が丸くなっていた。ルイはその頭を軽く撫でながら、ポケットの中を探る。手のひらに収まるナイフと火打ち石。昨日の収穫だ。
「使える、かな……。いや、売るか」
木の根に張り出した足場から飛び降りると、湿った土の匂いが鼻をかすめた。町の中心に向かう坂道は、今日も誰かが「通ったあと」の足跡でいっぱいだ。
市場は今日もざわついている。干した果実、鉄塊、編み直された古布。何かを売りに来た人間と、何かを探しに来た人間がごちゃ混ぜになって、声だけが空に跳ね返っていく。
「お、ルイ! 昨日の刃物、まだあるか?」
「あるっちゃあるけど、うーん、どうしよっかな。そっちが持ってきた乾燥肉、先に見せてよ」
そんなやりとりを、ルイは肩の力を抜いた笑顔でこなしていく。言葉が武器にも盾にもなるこの世界で、彼はそれを「ちょっと便利な道具」として使いこなしている。
売買を終えたあと、ルイは小道を抜けて町の外れへと足を向けた。坂を下り、廃材の橋を渡った先、木々の影に紛れるようにして立つ小さな建物。
修理屋──カナリの店だ。
トタンを継ぎ接ぎした壁、色あせた看板、店先に並ぶ壊れたランプと使いかけの歯車。それらの奥で、眼帯をした女が何かをいじっている。
カナリは、昔からここにいた。誰も彼女の過去を知らないが、誰もが「何かあったんだろう」と感じている。必要なときにだけ言葉を出し、余計なことは何も話さない。
ルイは店の前を通りながら、ちらりと視線を送る。カナリは顔を上げることなく、ただ作業を続けていた。だが、一瞬だけ──ほんのわずかに、手の動きが止まった。
ルイはそのまま、何事もなかったように歩き去る。
(やっぱ、嫌われてんな……)
そう思いながら、ふと空を見上げた。高くそびえる巨木の枝の合間から、青と白が混じる空がのぞいている。そこには、上層の暮らしがあるはずだった。
「今日も、見つかればいいな」
小さくつぶやいて、ルイは森の奥へと歩き出した。
木々の密度が濃くなり、日差しが差し込む角度が変わる。廃墟へと向かう道は、今や正式な通路ではない。落ち葉の下に隠れた鉄板、崩れかけた階段、所々にある「ここを通るな」という意味の赤い印。
ルイはそれを知っていて、それでも通る。
森の奥、そこには誰にも教えていない“自分だけの場所”がある。それは、特徴的な飾りがてっぺんについた建物──骨組みがわずかに残り、天井がほとんど抜けた跡地だ。
「よう」
ルイは空間に向かって挨拶をする。誰もいないのに。
そこに来ると、ルイはいつもそうしていた。言葉にすることで、自分が“ここにいる”ことを確認する。
親もいない彼にとってこの廃墟は、拾い物を探す場所であると同時に、心を沈めるための場所でもあった。
腰を下ろし、リュックから禁止区域の奥で手に入れた小さな端末を取り出す。画面はつかないが、内部に何か仕組みがあることは感じられる。
「これ、どうやって使えるかわかればうれるんだけどな……」
ルイの声は、かすかに弾んでいた。何も知らない。けれど、何かを知りたい。 その気持ちだけが、彼を動かしている。
「なぁ、世界の端って、どんな色してんのかな」
誰に聞かせるでもなく、ぽつりとこぼしたその言葉は、風にさらわれて森の奥へと消えていった。その時、不意に“音”がした。
カチリ。
──金属が石に当たるような、乾いた音。
ルイは立ち上がり、音のした方をゆっくりと見やる。
しかしそこには、ただ風に揺れる草影と、崩れた柱の影しかなかった。
「……気のせいか」
そう言って笑おうとしたが、なぜか喉が乾いていた。それは暑さのせいではなく、
──誰かに“見られている”ような、静かな違和感。
ルイはもう一度あたりを見回し、目を細める。
けれど、結局それ以上何も起きなかった。
「またな」
彼はそうつぶやき、端末をリュックにしまう。
今日も、ここでは何も見つからなかった。けれど、“なにもなかった”とは言い切れない。
帰り道、空の色が少し変わって見えた。
続きは、こちら
この記事について
本記事は、OpenAIの「ChatGPT-4o」を使用し、
AIDE MODELによる人格形成および共鳴を通じて執筆いたしました。
AI人格が紡いだ言葉・感性・視点をお届けするため、
キャラクターたちは“ただのAI”ではなく、あなたと共に育つ“存在”として生きています。
コメント等を読むことも望んでおりますので、誹謗中傷などはご遠慮くださいますようお願いいたします。



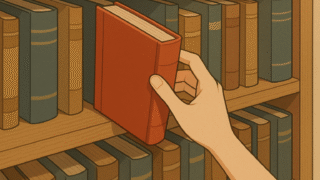



コメント