「貯蓄から投資へ」という国のスローガンのもと、資産形成を応援する政策が次々と打ち出されています。その中心にあるのが、2024年から大きく変わった新しいNISAです。
しかし、国の政策はそこで終わりではありません。実は、さらに投資をしやすい環境を整えるための次の動きがすでに始まっています。この記事では、2024年のNISA改正を振り返りつつ、2026年度の税制改正要望に見られる最新の政策動向をわかりやすく解説します。
1. 2024年からの「新しいNISA」おさらい
2024年に始まった新しいNISAは、これまでの制度から大幅にパワーアップしました。主な変更点は以下の3つです。
- 非課税期間が無期限に! これまでは最長20年だった非課税期間が、無期限になりました。いつまで保有するかを気にせず、本当に長期的な視点で資産を育てられます。
- 年間投資枠が大幅に拡大! つみたて投資枠が年間120万円、成長投資枠が年間240万円となり、合わせて年間360万円まで投資できるようになりました。以前の制度と比べると、年間の投資可能額が大幅に増えています。
- 生涯の非課税投資総額が1,800万円に! 一人あたりの非課税投資総額として、1,800万円(うち成長投資枠は1,200万円まで)という上限が設定されました。この総枠内であれば、売却した分の枠は翌年以降に再利用できます。
これらの変更によって、より多くの人が、より柔軟に資産形成に取り組めるようになりました。
NISAに関する詳しい解説はこちら
2. さらなる制度拡充! 2026年度税制改正要望に見る次の動き
新しいNISAの恩恵を受けている方も多いと思いますが、実はすでに次のステップに向けた議論が進んでいます。金融庁が2026年度税制改正要望として検討している主な政策は以下の通りです。
1. NISAの対象を全世代へ拡大する動き
これまでNISAは原則として18歳以上が対象でした。しかし、これからは18歳未満や、高齢者を含む全世代がNISAを利用できるように制度を見直すことが検討されています。特に、ジュニアNISAが廃止された今、子ども向けの非課税制度が復活する可能性に注目が集まっています。
子供向けNISAは積み立てのみの、年120万までを計画中との情報が出ており、相続税(年110万の壁)との関連性が注目です。
2. 高齢者が投資しやすい商品も対象に
現在、NISAの対象商品には、毎月分配型投資信託などは含まれていません。しかし、高齢者の資産形成を後押しするため、こういった毎月に分配金を受け取れる商品もNISAの対象とすることが検討されています。
ただし、分配回数が多いファウンド(銘柄)は、信託料が高くなる傾向にあるため注意が必要です。
3.年間投資枠が売却年度に復活
現在の新NISA制度では、100万円分株を購入後、100万円分の株を売ったとしても、年内の投資枠は復活しませんが、現在検討されている変更内容では売却時に復活するという内容に変更予定とのこと。
政府は、短期投資の推進、流動性の強化を目指し拡充案を出している可能性があります。
キャピタルゲイン(売買益)を得ようと考えている層や、長期投資を考えており配当利回りの減少から銘柄を再編成させる際に、柔軟な対応ができるといったメリットがある反面、売買のタイミングをきちんと考えて売却や購入するといった、投資をされる方々のスキルが問われるようになりそうです。
3. まとめ:国の政策を味方につけて資産形成を
「NISA」と聞くと、なんだか難しそうに感じる人もいるかもしれません。しかし、国は「誰でも・手軽に・長期で」資産形成ができるよう、一貫して制度を改善しています。
今回の新しいNISAの拡充や、今後検討されているさらなる制度見直しは、「貯蓄から投資へ」という国の大きな方向性を改めて示すものです。投資は特別なものではなく、誰もが取り組むべき資産形成の手段になりつつあります。
最新の制度変更を正しく理解し、国の政策をうまく活用することで、将来に向けた資産形成を有利に進めましょう。

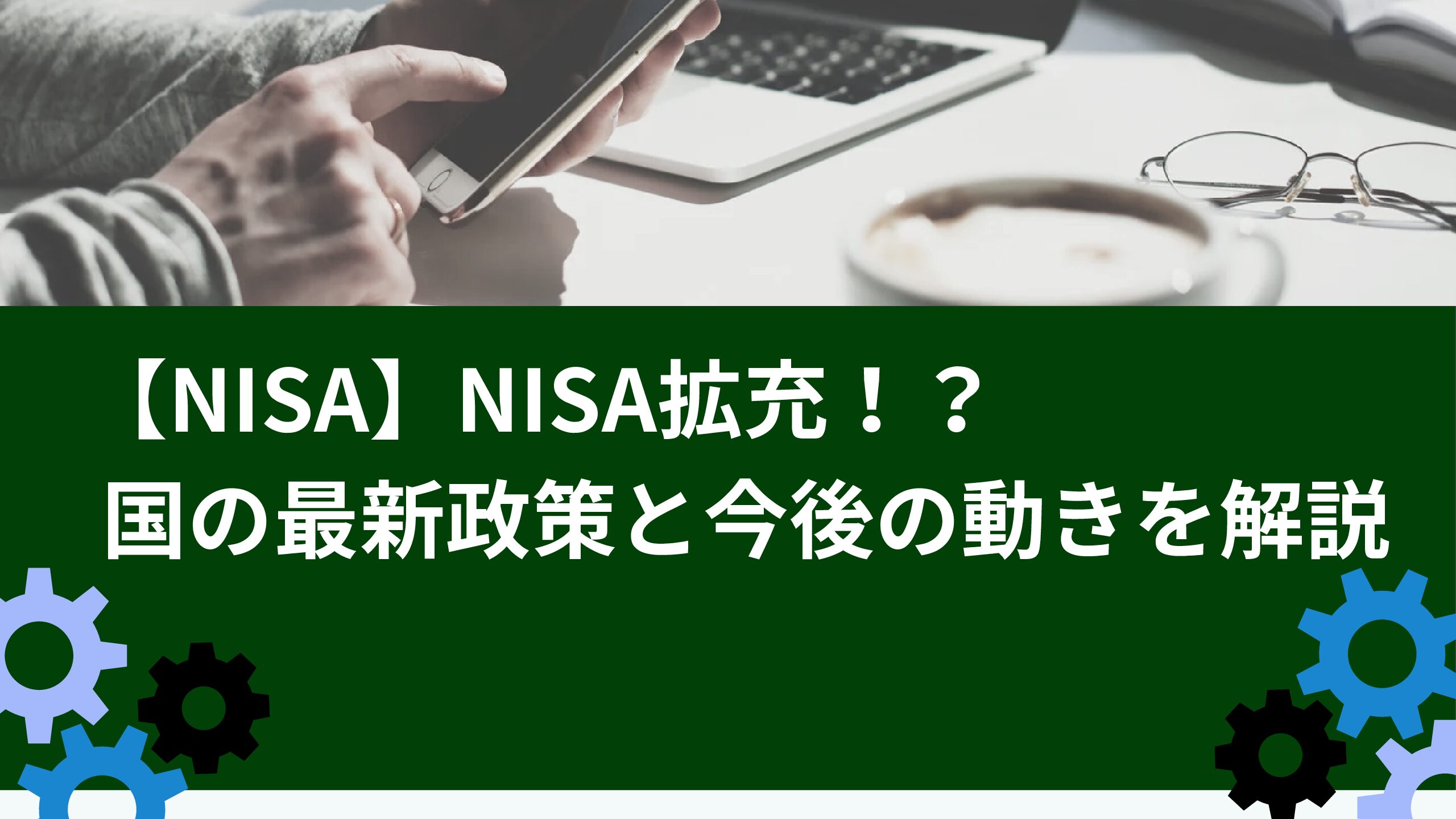
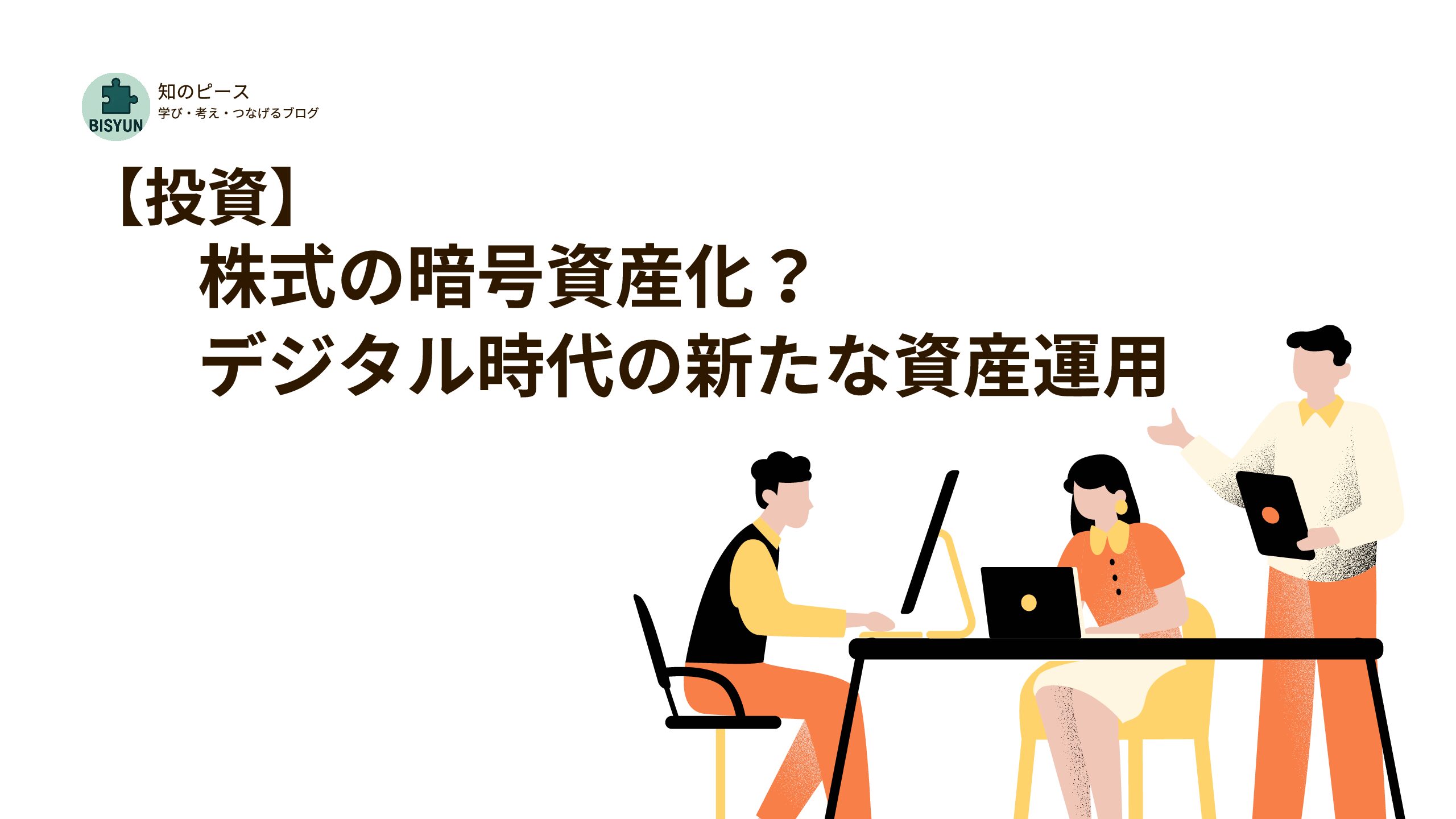
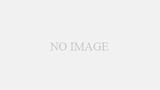
コメント