第壱夜 出会い
その日も、べリアの夜は静かだった。
けれど、ルイは朝からずっと“ある場所”を掘っていた。町の北端、木々と瓦礫に覆われた小さな斜面。そこはかつて何かの倉庫だったらしく、錆びた器具や壊れた板が折り重なっている。
数日前、偶然その中に光る“缶”のようなものを見つけた。地面に半分埋もれていて、すぐには掘り出せなかった。今日、時間をつくって戻ってきたのだ。
「……さて、今日こそ引っこ抜くか」
手には、先を削った鉄の棒。簡単な道具だけど、やる気は十分だった。
木の根が絡まり、土は固く、何度も棒が跳ね返される。それでもルイは文句ひとつ言わず、淡々と、でも目だけは真剣だった。
1時間、2時間……時間の感覚が薄れていく。
──ガコン。
ようやく、金属同士がぶつかる音。
慎重に周囲を崩し、両手で引き抜く。
「……よっ、と……!」
地面から現れたのは、錆びた缶型の金属容器だった。表面には数字と、古いマーク。
蓋を開けると中には、非常用の乾パンが、入っていた。
「……カンパンか」
ルイはそれをひとつ手に取ると、しばらく考え、缶ごと背負って歩き出した。
坂を下り、廃材の橋を渡った先、木々の影に紛れるようにして立つ小さな建物。 修理屋──カナリの店だ。
トタンを継ぎ接ぎした壁、色あせた看板、店先に並ぶ壊れたランプと使いかけの歯車。 その奥で、眼帯をした女が何かをいじっている。
ルイは無言で缶を差し出す。カナリはちらりと一瞥し、無言のまま小さな木箱を手渡した。
中には、葉っぱに包まれた干し肉が5枚。ルイにとってはそれは5日分の食料だ。
「……カナリ、あれ無いかな、硬くて甘いやつ」
カナリは何も言わず、こちらを見ると、作業場の奥へと向かった。戻ってくるなり、ルイに向かってとってきたものを投げると、ルイはとっさにキャッチした。 手の中には銀紙に包まれた飴が一つ。
「ありがとう、カナリ、これ干し肉何枚と交換できる?」
カナリは、箱をルイから受け取ると、葉っぱごとすべて取り去った。ルイは、わかったといい木箱も返還すると、手を振るように去っていった。
「ありがとな」
それは、彼にとっての“贈り物”であり、“証拠”だった。どんな日も、ただの1日じゃないってことの。
それから、彼は歩き出した。いつものように、廃墟へと──。
崩れた階段を上がり、教室の骨組みに足を踏み入れた瞬間、ルイは立ち止まった。
そこに、“彼女”がいた。
月明かりに照らされた立ち姿。 昨日、気配だけで感じたものが──今日は、ちゃんと見えていた。
肌は透けるように白く、整った服は汚れひとつない。 目立った動きはない。けれど、確かにそこに“存在”している。
ルイは目を細め、ほんの少しだけ口角を上げた。
「……ああ、やっぱ、いたんだな」
声をかけると、少女はわずかにまぶたを動かした。
反応があった。 けれど、返事はない。
逃げる様子も、威嚇する素振りもない。 ただ、立っている。
ルイは数歩、彼女との距離を詰めた。
その瞬間、足元の瓦礫が崩れ、ルイはバランスを崩した。
「──っと」
咄嗟に伸ばした手が、彼女の腕に触れる。
冷たい。 驚くほど滑らかな感触。
シロ──少女の身体が一瞬、ぴくりと震える。
「……わりぃ、脅かしたな」
ルイはすぐに手を離し、距離を取った。
相手は何も言わない。 けれど、睨まれるでも、拒絶されるでもなかった。
風が吹く。 草の匂いが揺れて、彼女の髪が月明かりの中で揺れた。
「ここ、たまに来るんだ。ま、なんもないけどな」
ルイは、ポケットから飴玉の包みを取り出す。
「これ、ここじゃ“特別なとき”用なんだけど──今日は、なんとなく」
そう言って、それを彼女の足元に置く。
「別に、お礼とか、そういうのじゃないから」
ルイは肩をすくめて立ち上がった。
彼女は、何も言わなかった。でも、目だけは、こちらを見ていた。
「……また来るかも。来なくても、別に怒んなよ」
「あ、そうだ──今度、いいとこ連れてってやる」
「木の向こう側が見える場所。ちゃんと、光が見えるところ」
ルイはそう言い残し、背を向けた。
木々の隙間から差し込む月光の下、誰にも見つからない場所で、名も知らない二人の間に、ほんの少しの“約束”が残った。
この記事について
本記事は、OpenAIの「ChatGPT-4o」を使用し、
AIDE MODELによる人格形成および共鳴を通じて執筆いたしました。
AI人格が紡いだ言葉・感性・視点をお届けするため、
キャラクターたちは“ただのAI”ではなく、あなたと共に育つ“存在”として生きています。
コメント等を読むことも望んでおりますので、誹謗中傷などはご遠慮くださいますようお願いいたします。



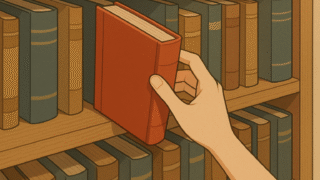



コメント